はじめに
4月22日は #聖徳太子 の御命日。令和四年の今年は #千四百年忌 にあたり #四天王寺 では大法要が行われます
目次
本文
4月22日(本日)、四天王寺さんでは令和四年の聖霊会(しょうりょうえ)。
太子の命日(旧暦2月22日)の大法要で、今年は、聖徳太子千四百年御聖忌慶讃大法会の結願となり、通常よりも規模の大きな行事となるそうです。

四天王寺の六時堂と石舞台で、天王寺楽所(てんのうじがくそ)*1による舞楽と四天王寺僧侶による声明が奉納されます
開始は正午頃、終了は午後8時頃の長丁場(この記事を書いている間も進行中です)

千と千尋の神隠しで、温泉に集団で登場して有名になった 蘇利古(そりこ*2)


#四天王寺 #聖霊会(しょうりょうえ)#蘇利古(そりこ) pic.twitter.com/MhnqKgHfMy
— 開物発事 (@Kai_Hatu) 2022年4月22日
長めの30秒追加。
#四天王寺 #聖霊会 #蘇利古(2)長めの30秒 pic.twitter.com/Py9q8wRNnm
— 開物発事 (@Kai_Hatu) 2022年4月22日
聖霊会の様子(百年に一度の結縁綱が張られています)







赤いぼんぼり(名前を知りません😅)の間を通る、白い結縁綱(けちえんづな)が見えるでしょうか。
今年は聖徳太子の千四百年忌。
これが張られるのは百年に一回。




【京都・六角堂にも張られた結縁綱】
*1:京都の宮廷の「大内楽所(おおうちがくそ)」、奈良の大社寺の雅楽の「南都楽所(なんとがくそ)」とともに、平安時代以来、日本の雅楽伝承を担う三方楽所(さんぽうがくそ)のひとつ。明治以降、楽所の楽師たちが、東京へ召され、三方楽所は一旦廃絶。しかし、この事態を憂いた民間の有志が明治17年、四天王寺の「聖霊会」伝承グループ「雅亮会」を結成。現在も続いています。天王寺楽所・雅亮会HPより
*2:日本の雅楽の曲名。高麗壱越(こまいちこつ)調、小曲に属する。4人舞(四天王寺では5人舞)。前奏として意調子が奏される。舞人は雑面(ぞうめん)をつけ、白楚(ずわえ)と呼ばれる短い棒を持つ。古来、竈(かまど)祭の舞ともいわれ,応神天皇の時代に百済人の須々許理(すすこり)がもたらしたものともいう。ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より

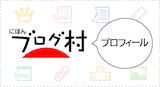 ポチっとお願い
ポチっとお願い