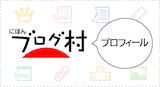はじめに
青森市はかつて #安潟(やすがた)と云われた広大な海辺の湿地帯。#善知鳥神社 境内の #うとう沼 はそのわずかなこん跡。ここで #菅江真澄 が詩を詠み、#棟方志功 の子どもの頃の遊び場でした
目次
- 善知鳥神社(うとうじんじゃ)御由緒
- 善知鳥神社 境内
- 安潟、うとう沼(こん跡)
- 菅江真澄の歌碑、謡曲・善知鳥の舞台
- 伝 芭蕉翁 句碑
- 境内 弁財天宮、龍神の水
- 海鳥 善知鳥(うとう)
- 棟方志功 生誕の地
本文
善知鳥神社(うとうじんじゃ)御由緒

(40.8265818, 140.7429595)/青森県青森市安方2-7-18/青森駅から東に徒歩20分。専用駐車場あり
御祭神:【宗像三女神】多紀理毘売命(タギリ・タゴリヒメ)、市寸島比売命(イチキシマヒメ)、多岐都比売命(タギツ・タキツヒメ)

御由緒の文末には「善知鳥神社は青森発祥の地」と書かれています。前半が読みづらいので、wikiよりコピペ。
御由緒wikiより)第十九代允恭天皇の時代に、善知鳥中納言安方(うとうちゅうなごんやすかた)が勅勘を受けて外ヶ浜に蟄居していた時に高倉明神の霊夢に感じて干潟に小さな祠を建設し、宗像三神を祀ったのが神社の起こりと伝わる。安方が亡くなると、見慣れない一番の鳥が小祠のほとりに飛んできて雄はウトウと鳴き、雌はヤスカタと鳴くので、人々はこの鳥を安方の化身として恐れ敬ったが、ある日猟師が誤ってこの雄鳥を狙撃してしまい、以後雄鳥によって田畑が荒らされた。狙撃した猟師も変死したため、祟りを恐れた同郷の人々は雄鳥を丁重に弔った。…その後、坂上田村麻呂の時代には同祠は荒廃していたため、大同年間に田村麻呂により社殿が造営されて再興された。建仁から天正期(1201年~1592年)の間は同地を支配した領主の南部氏により厚く崇敬されて庇護され、南部氏の騒動で同地が江戸時代に津軽氏の支配地になっても、同氏により手厚い庇護を受けた。明治時代に入り、1873年に郷社、1876年に県社に昇格。1907年7月に稲荷神社、同年9月に海津見神社を合祀し、現在に至る。
善知鳥神社 境内







安潟、うとう沼(こん跡)

境内のうとう沼。かつては現在の青森市街に相当する海辺の広大な湿地帯・安潟でした。善知鳥神社のここがそのわずかな名残りです。



菅江真澄(すがえますみ)は、三河国・豊橋の出身で、江戸後期の旅行家、今で言う博物学者、民俗学者。
信濃を経て出羽・陸奥・蝦夷といった日本の北辺を旅し、著作に各地の記録を残しました。



由緒に書かれた「誤って鳥を撃ち変死した漁師の話」が、謡曲「善知鳥」の素材でしょうか。
伝 芭蕉翁 句碑

境内 弁財天宮、龍神の水





海鳥 善知鳥(うとう)
社務所に善知鳥の写真が飾ってありました。

棟方志功 生誕の地
安方は、版画家・棟方志功(むなかたしこう)の生誕の地。
棟方志功が子供の頃は、善知鳥神社の境内は遊び場だったそうです。長じて結婚式を挙げた氏神さんでもありました。
参考に。大阪北浜の洋菓子店・五感の喫茶室にある棟方志功のガラス絵。
天女のモチーフは有名ですね。