はじめに
天理市の東 #大国見山 麓の #桃尾の滝 古くは#布留の滝。23メートル。滝つぼがなく近づいて見上げると大迫力。もと義淵が開いた龍福寺の境内地。後に真言密教道場として栄え、今は昼なお暗い不思議空間
目次
本文
天理大学や石上神宮のある天理市中心(天理駅)から車で約10分。国道25号線から入った山道を進むと無料駐車場があります。
ご覧のように滝つぼがなく、真下まで近づいて見上げることができます。


説明板文字起こし)桃尾の滝は、布留川の上流桃尾山にあり、高さ約二十三メートル、大和高原の西端を南北に走る春日断層の中では最大の滝です。このあたりは、かつて桃尾山蓮華王院龍福寺の境内地でした。和銅年間、義淵によって開かれた龍福寺は、中世には寺領五百石を有する真言密教の大道場として栄えましたが、明治にはいって廃絶し、かつての阿弥陀堂跡には現在報親教大親寺の堂が建っています。『布留の滝』として古い和歌集にも詠まれた桃尾の滝は、古くから行場として知られ、七月第三日曜日には夏の安全を祈願して『滝開き』の神事が行われます。今はまた ゆきても見ばや 石の上(いそのかみ) ふるの滝津瀬 跡をたづねて(後嵯峨天皇*1)

かつては義淵僧正が開いた龍福寺・境内地
かつては奈良仏教の 義淵(ぎえん) が開いた龍福寺(現在は廃寺)の境内地で、後に真言密教の道場になったとのこと。
義淵は 天武天皇の皇子とともに飛鳥の岡本宮で養育されたと伝えられており(扶桑略記、東大寺要録)、僧正として、行基*2や弓削道鏡(ゆげのどうきょう)*3らを弟子としました。
古代妄想は外れることも多数ですが、たまに途切れることなく、つながりが突然現れたりします。
阿刀氏は弘法大師・空海さんの母方の血筋とされています。繋がりは不明です。
後に真言密教の道場










雲ひとつ見えない晴天の朝。


アラハバキ解・汎日本古代信仰の謎に迫る(新章公開)
第25章)ヤマトと蝦夷の境界で生まれた馬頭の信仰

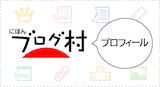 ポチっとお願い
ポチっとお願い