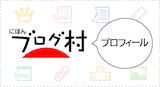はじめに
人にものを贈ったりするとき「熨斗(のし)を付ける」といいますが、起源は #伊勢神宮 創設期 #海女さん の献上物にさかのぼるんですね #熨斗あわび #倭姫
目次
本文
伊勢神宮御料鰒調製所(いせじんぐうごりょうあわびちょうせいしょ)
先日紹介した海士潜女神社(海女御前)がかつて鎮座していた鎧崎(よろいざき)に、伊勢神宮御料鰒調製所(いせじんぐうごりょうあわびちょうせいしょ) があります。

(34.4133568, 136.9269107)/三重県鳥羽市国崎町/海士潜女神社より徒歩5分。国崎漁港(くざきぎょこう)から徒歩10分
伊勢神宮では、一年間で約1500回に及ぶ祭祀を滞りなく斎行するために、朝夕の神饌(しんせん、神様にお供えするお食事)のほか、様々なお供物を自給自足します。
その生産地を 御料地 と云い、ここ鰒調製所(あわびちょうせいしょ)では、熨斗あわび をつくっています。
御料地は、神宮神田(米)、神宮御園(やさい)、御塩浜(御塩)のほか、熨斗あわび、⼲鯛(ひだい)、⼟器(素焼きの皿など)、機殿(はたどの、絹・麻)があります。


藻場(もば)守る 国崎(くざき)の海女ら 晴れ晴れと 得し海幸(うみさち)を われに示せり
伝説の海女「お弁」が倭姫に献上した鰒(あわび)の伝承をモチーフに、現代の海女さんのいきいきとした様子を描いた素敵な歌ですね。


国崎(くざき)熨斗(のし)あわびづくりの成立は古く、この地は「ミケツクニ」と呼ばれています。伝承では倭姫命(やまとひめのみこと)が国崎の湯貴(ゆき)の潜女(かづきめ)が奉った鰒が美味であったため、国崎を御贄所にしたという(補足、海士潜女神社由緒)。現在は神宮(内宮・外宮)の三節祭(6月・12月の月次祭、10月の神嘗祭)のため、大身取鰒、小身取鰒、玉貫鰒、甘掻鰒(あまかきあわび)、干栄螺(かわきさざえ)を調進しています。すべての熨斗あわびが伝統的技法を受け継いだ長老たちによって、鎧崎にある神宮御料鰒超生所で潔斎して調整します。
参考に、海士潜女神社・拝殿内に飾られていた熨斗あわび。中央が大身取鰒、右が小身取鰒、左が玉貫鰒。



毎年6〜8月に作業が行われます。
あわびひとつひとつ、皮をむくように薄切り、ヒノキで造られた干し場で干すそうです。
一回に使われる鮑は200㌔。
伊勢神宮ですから、神明鳥居。



海の博物館 熨斗あわび 展示
熨斗袋の「のし」は、あわびのことだったんですねぇ😀



明治の初期まで行われていた 御潜神事(みかづきしんじ)
平成十五年と二十五年に、伊勢志摩の海女さん達が鎧崎の磯に集まり、鰒採りが行われたそうです(ポスターは平成二十五年のもの)

鎧崎の倭姫 旧蹟地
神宮御料鰒調整所から、鎧崎の高いところに登ると、倭姫(やまとひめ)の旧蹟地の碑が建てられていました。