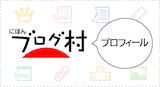はじめに
景色のよい #忍阪街道 の道標のところから東の山間の坂道を歩くと #舒明天皇(第34代)#忍坂段ノ塚古墳。日本最初の #八角墳。国土をあまねく支配する権威のカタチは天皇御陵にのみ許された形
目次
本文
景色のよい忍阪街道
忍坂坐生根神社、玉津島明神の前を通り、忍阪街道を南に進むと、舒明天皇陵への道標が立つT字路のところにやってきます。

緩やかな坂道を、日の出の東の方向に向かいます。


忍阪は、街道筋の景色が良いところです。



舒明天皇 忍坂段ノ塚古墳
(34.5073601, 135.8755773)/奈良県桜井市忍阪556/駐車場あり
飛鳥時代、推古天皇の後を継ぎ、第34代となった舒明天皇(息長足日広額天皇)の御陵。
ここから、八方あまねく国を支配する権威のカタチの陵墓が現れ、
聖徳太子の仏教・転法輪(釈迦の教えとともに、日本では八方を示すと考えられた)の思想以降、日本の国家観が大きく変化したことを示しています。


なお、舒明天皇の皇后は、後の皇極天皇(35代)、斉明天皇(37代)として重祚(ちょうそ)した宝皇女(たからのひめみこ)。
宝皇女は、第40代・天武天皇の御母上ですが、実は出自がよくわかっていない女帝。
天武天皇の「大海人皇子」の名から類推するに、海人系、つまり安曇氏と繋がり深い女性ではなかったかと考えています。
安曇氏の協力という観点では、北九州から瀬戸内海をやって来た神功皇后を彷彿とさせます。
神功皇后(気長足姫、おきながたらしひめ)は、古墳時代の第14代・仲哀天皇の皇后で、実質的に日本の最初の女性天皇ともされています。

岡本宮の詳しい所在は不明ですが、先日紹介した、明日香の岡寺の麓から西の一帯(飛鳥京)のどこかに、あったものと考えられます。