はじめに
大阪府高槻市 #継体天皇 王墓陵が定説化した #今城塚古墳。濠の外周、65mの張り出しに #埴輪まつりのステージ。出土状況を復元して1区から4区までに200体以上。#今城塚古代歴史館 の展示とあわせて埴輪、古代の王宮・祭祀を考えるのによい史跡です
目次
- 埴輪まつりのステージ・4区(宮の門前)
- 埴輪まつりのステージ・3区(宮の内・前)
- 埴輪まつりのステージ・2区(宮の内・中)
- 埴輪まつりのステージ・1区(宮の内・奥)
- アラハバキ解 第41章公開 ヒスイのものづくり史(5)河内期・物部氏の興隆と難波玉作部
本文
前回記事。
埴輪まつりのステージ・4区(宮の門前)
白鳥の列や牛・馬の列、武人や鷹飼人が並べられ、塀の近くには、門をまもるかのように盾や力士が配置されています
大王の宮の門前の様子です。市(いち)の賑わいにも見えますが、宮の門前を守る守備体制(守備隊)を表現しているという解釈でしょうか。
古代の力士には王家を守る特別な役割があったんでしょうか。スタイルが昔も今も変わらないところが興味深いです。







埴輪まつりのステージ・3区(宮の内・前)
太刀の列と水鳥の列、盛装した男子など、また日本最大の祭殿風の家や楽座の男子が所狭しと配置されています。中央には両手を高く揚げる巫女を先頭に、供物や祭具をもつ巫女が2列に立ち、矢を入れる靫(ゆぎ)や盾もあります。もっともにぎやかで祭祀場の中心的な空間です。4区との間の塀に設けられた門には、扉も表現されていました。4区との間の塀に設けられた門には、扉も表現されていました






埴輪まつりのステージ・2区(宮の内・中)
太刀(たち)の列と甲冑(かっちゅう)の列が並び、開放的な祭殿風の大きな家や鶏、巫女、さらに小型の家も配置されています。3区との間の塀には門が設けられています
いずれの門にも扉が造作されていますが、3区-2区-1区と直線に並ぶ空間配置。門には何かの霊的イメージがあったように思います。
鶏(常代の長鳴鶏、とこよのがなきどり)とのセットで、天の岩戸も思い浮かべます。



埴輪まつりのステージ・1区(宮の内・奥)
器台と蓋(きぬがさ)の列、片流れの家。また魚と鳥の絵のある祭殿風の家と鶏が配置されています。亡き大王が安置されている空間を暗示し、2区との間の塀には門がありました
一番奥の片流れの家に、大王の亡骸が安置されたというイメージでしょうか。まさに奥の院。
神社でよく見る流造り(屋根の前方が流れるように長い様式)に通じるものがあるのかも知れません。



河内期・物部氏 #倭の五王時代 に台頭し行政全般、特に軍事・祭祀において王権の代執行者となり #巨大前方後円墳の造営 の動員力と広範な #モノづくり パワーを背景に #古代河内湖 沿岸をほぼ掌握しました
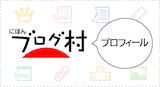 ポチっとお願い
ポチっとお願い